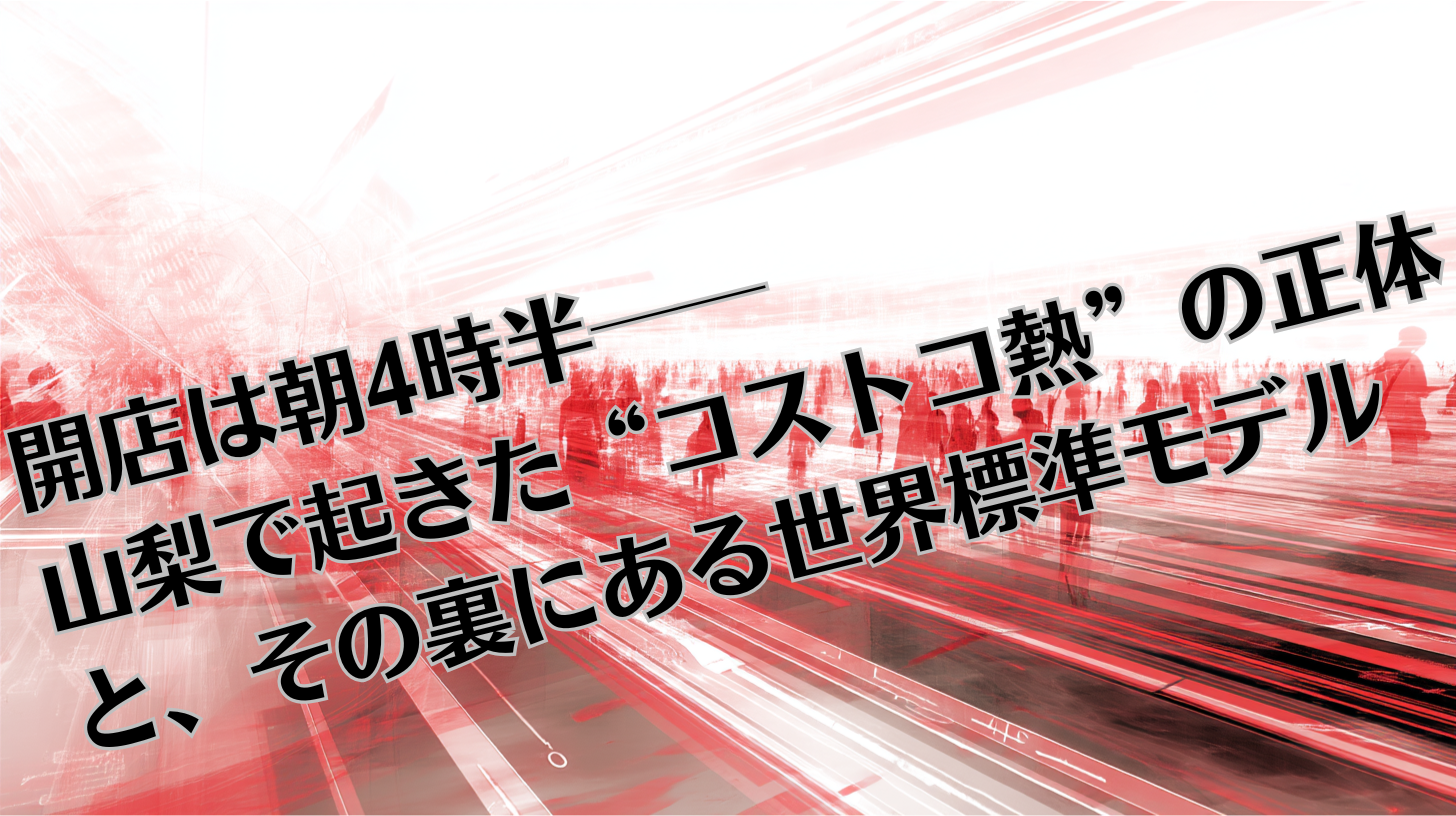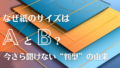はじめに
2025年4月11日、山梨県南アルプス市にコストコの新店舗「南アルプス倉庫店」がオープンしました。山梨県初進出となるこの店舗は、事前告知段階から大きな話題を呼び、オープン当日にはその注目度の高さを証明する事態が発生します。あまりの人出により、当初予定していた開店時間を2時間半も前倒しし、午前4時半という異例の時間に開店することとなったのです。
この現象は、単なる人気チェーンの新規出店という枠を超えています。なぜなら、コストコは既に“安売り量販店”というイメージを超えて、「地方経済の重心」「体験型ショッピングの象徴」「収益性に優れた世界標準モデル」として確固たるポジションを築いているからです。
本記事では、コストコのビジネスモデルの核心を多角的に分析します。収益の柱となる会員制度、地方における集客モデルの成立メカニズム、出店戦略と規模の経済、そして非日常性を軸にした“ブランド体験”の提供まで、グローバルな文脈も踏まえながら解説していきます。
利益の源泉は「商品」ではない──会員費で支えるビジネスモデル
コストコの事業は一見すると、圧倒的な商品販売力に依存しているように見えます。1店舗あたり年間売上は160〜180億円超とも言われ、大手ショッピングセンターの複数店舗分に匹敵します。にもかかわらず、営業利益率は3〜4%程度と控えめです。理由は単純で、コストコは「商品では儲けない」モデルを採っているからです。
同社の収益の本丸は、実は「年会費収入」です。2025年現在、日本におけるゴールドスター会員の年会費は4,840円(5月から5,280円)、法人向けのビジネスメンバーも同額で、さらにプレミアムランクである「エグゼクティブ会員」は年会費9,900円です。日本ではこのエグゼクティブ会員の割合が約6割に達しているとも報告されており(出典:ITmedia)、他国と比較しても極めて高いアップグレード率です。
コストコ全体の会員数は世界で1億3,900万人、日本だけでも600万人以上を抱えており、この会費収入が営業利益の50%以上を支えているという極めてユニークな収益構造を築いています(出典:商人舎ニュース)。
このモデルでは、「会費で利益を確保し、商品価格を限界まで下げて集客する」という構図が成立します。つまり、低価格は利益のためではなく、会員満足のための投資として位置づけられているのです。
数字で見るコストコ日本法人──成長する地方発ビジネス
コストコ日本法人の業績は、きわめて堅調です。2022年度には約5,700億円の売上を計上し、2024年度にはさらに拡大しています(出典:note.com)。これを当時の31店舗で割ると、1店舗あたりの平均売上は約183億8,700万円。これは、同規模の国内流通業(例:GMSやSC)の数倍の売上効率です。
この驚異的な効率の鍵は、「集客圏の設計」にあります。コストコは都市部の密集出店を避け、広域から車で集客できる地方・郊外立地を基本としています。南アルプス店も、山梨県内のみならず静岡や長野、さらには東京からも来店者を集め、開店当日は国道沿いで大渋滞が発生するほどでした。
上述の通り、日本全国での会員数は600万人超とされていますが、これは家族カードを除く主会員の数。家族カードを含めれば、稼働中のカードは1,000万枚近い可能性もあります。
コストコはその圧倒的集客力により、周囲数十キロ圏の商業構造に影響を与える“商業装置”となっており、地域のインフラとも言える存在になりつつあります。
出店加速の裏にある緻密な戦略とハードル
2025年4月時点で全国に37店舗を展開するコストコは、今後数年間でさらに20店舗以上を増やし、「2030年までに60店舗体制」を公式に掲げています(出典:マイナビ)。
ただし、その道のりは平坦ではありません。出店に求められる条件は非常に厳格で、以下の3点が基本要件です:
- 半径10km圏内に50万人以上の人口
- 敷地面積:1万坪(33,000㎡)以上
- 駐車場:最低800台、理想は1,000台以上
このような用地を確保できるのは、都市部よりむしろ郊外や地方の中核都市です。そのため、滋賀県東近江市や沖縄県南城市など、地方自治体が積極的に誘致に動いている例が増えています。
地方におけるコストコの誘致は、「雇用創出」「税収増」「周辺インフラ整備」のトリガーとして位置づけられつつあります。実際、南アルプス市でも数百人規模の雇用が生まれ、交通インフラの再整備が進められました。
一方で、交通渋滞、地元小売業の競争激化、騒音などの課題もあります。これらに対してコストコは、来店時間の分散施策や地域との連携イベント、店舗限定の地産商品販売など、地域との共生を意識した対応を強化しています。
「価格」ではなく「体験」を売る──ブランドとしてのコストコ
価格が安い──それはコストコの入口に過ぎません。実際に、すべての商品が競合他社より安いわけではなく、単位当たり価格で見ると同等かそれ以上のケースもあります。それでも人々が通い続ける理由、それが「体験の総合価値」にあります。
巨大なカートで広大な倉庫を回遊する楽しさ、圧倒的なボリュームの商品群、1個300g超のベーグル、家族でシェアできるピザ1ホール、ドリンク飲み放題付き180円のホットドッグ──これらすべてが“非日常のエンタメ”として顧客の記憶に残ります。
日本ではこの“体験価値”をさらに高めるべく、食品のローカライズが進められています。プルコギビーフや寿司盛り合わせ、シーフードピザ、国産豚使用のシュウマイ──これらはすべて「外国の雰囲気はそのままに、日本の食卓に馴染む」商品設計の成果です。
また、精肉・青果・鮮魚などの生鮮部門では、国内仕入れと海外仕入れを適切にミックスすることで、品質と価格のバランスを維持。加えて、カークランドブランドによるコストパフォーマンスの高いPB商品展開も、他社にはない強みとなっています。
地方に根を張る「世界標準モデル」──コストコは“消費体験”のアップデート装置
山梨県南アルプス市における開店フィーバーは、コストコが単なるディスカウント業態を超え、地方における“目的地型施設”として定着しつつあることを証明しています。
コストコの強さは、グローバルで培ったスケールメリットを活かしつつ、日本市場に適応する柔軟さを備えている点にあります。「世界標準の収益構造」と「地域に根ざした購買体験」を両立しているからこそ、成長を続けられるのです。
今後、60店舗体制、さらには100店舗構想の実現に向けて、日本の商業地図はさらに塗り替えられていくことでしょう。単なる小売店としてではなく、地域経済、インフラ、生活文化に影響を与える“ハブ”として、コストコの存在はますます重要性を帯びていくはずです。
そしてその成長を支えているのは、どこか遠くの投資家でも、匿名の流通アルゴリズムでもなく──毎週末、大きなカートを押しながら、あの巨大倉庫の中でワクワクしている“あなた”自身なのかもしれません。